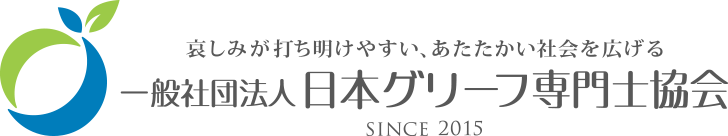グリーフケアの風景 Landscape
沈黙の中に溢れる想い

こんにちは。グリーフ専門士、寿月です。
日本グリーフ専門士協会では、大切な人や身近な人と死別された方に向けて、わかちあいの会やカウンセリングなど想いを語る場をご用意しています。
ですが、話したいと思って来てくださっていても、その時になったら言葉が出てこないということもよくあること。
今日は2月に開催された清水伶 映像インスタレーション展
【あなたがいない「 」を、どう埋めるかさがしています―何かを失いながら生きていく私たちの声とグリーフケア―】
その初日のトークショーの内容を踏まえて、「語る」をテーマにグリーフケアで大切なことを見つめていけたらと思っています。
それでは今日も書き進めてまいりましょう。
想いを語るきっかけは人それぞれ
トークショーのテーマは「アートはケアを語れるか?」でしたが、ケアの在り方や本質に触れる内容だったように思います。
登壇されたのは、
このアート展を主催したアーティストの清水伶さん、
NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]で各種プログラムの企画を手掛けていらっしゃる堀内菜穂子さん、
そして、日本グリーフ専門士協会の井手代表でした。
口火を切られた清水さんの言葉でとても印象に残ったのが、「その世界にいると、その世界にいる人しか受け入れないような風潮になる気がする」という独り言のような、投げかけのような言葉。
経験した人と経験していない人の間にある見えない壁のようなもの、アートに造詣が深い人とそうじゃない人という分断。
分かる(知っている)世界にいる人と、分からない(知らない)世界にいる人。
それぞれその内側からみた世界がそれぞれの目の前に広がっている。
自分から見えている景色が常識と言い切れるのか。
そんな大きな問いをいただいたように、私は感じました。
それを受け、[AIT/エイト]の堀内菜穂子さんが、「知識がなくても本質が見える」というお話をされました。
堀内さんは、医療や福祉の現場とつながり、「メンタルヘルス」とアートの接続、芸術の流用性を模索されています。
実際に福祉を必要とする方たちとの関わりの中で、アートの知識を持たないからこその多様な捉え方を目の当たりにしてきたそうです。
ある方は、ある絵を見て「おじいちゃんに似てる」とお話され、作品を通じてその方の想いに触れられた。また、色や形、目に映る単純なものから言葉にしていただくことで、最終的には家族のお話に行きつくこともあるそう。
そのようなお話を聴き、私はある経験を思い出しました。
夫が亡くなって数年後のある日、近所の小さな美術館に足を運んだ時のこと。
私はそこに展示されていた一枚の絵をみて、涙が止まらなくなったのです。
その絵には人物の後ろ姿が描かれていました。その背中は、言葉にならないような苦しみを背負ってしまって途方に暮れているように私からはみえました。
いつまでの絵の前で立ち尽くし泣いているものだから、美術館のスタッフの方が声をかけてくださいました。
私は、見ず知らずのその方に、夫が亡くなったことを自然と話していました。
あの絵に描かれている人の後ろ姿が自分と重なってみえること。
私を残して亡くなった夫の後ろ姿のようにも思えること。
夫も途方に暮れているのではないか。
一人で立ち尽くしているのではないか。
助けてあげたい。そばにいるよと手を握ってあげたい。
遠く離れてしまい、姿も見えない、声も聞こえない、触れることも支え合うこともできない私たち。
こんなに想っているのに手が届くことはなく、手放すこともできずにいて……。
そんなことをとめどなく話した記憶があります。
内側に閉じ込めていたつもりはないけれど、もしかしたらアートという媒体を通したから表面に浮かんできた気持ちかもしれないし、その絵が感情を出す手助けをしてくれたのかもしれません。
言葉にできない気持ちを抱えている
それぞれの立場、さまざまな視点からのお話の展開の中で、井手代表からは、グリーフケア=語りましょうではないというお話がありました。
状況によっては、言葉にしたくないことがあるかもしれない。
話したいと思っていても、どんな言葉でも足りない、追いつかないと感じている人もいます。
沈黙にもさまざまな形があるということ、そして、沈黙も尊重されるべき一つの表現であること。
私自身、夫や両親を亡くした後、自分が感じている気持ちや状態を言葉にすることがとても難しかったです。
あまりにも困っているし、あまりにもつらいし、あまりにもややこしいので、言葉が追いつかない。
頭の中や心の中にも言葉にまで育たないめちゃくちゃにもつれた毛糸の山がいくつもいくつもあって、自分でもどこから手をつけていいかもわからないのです。
やっとやっと言葉にした「しんどいよ」に対して、「だよね。わかるよ」と言われただけで、なんだかもう違うと思ってしまって次の言葉が紡げない。
もともと話すことがあまり得意ではないのですが、死別の後は特に「話して」と言われることが苦痛でもありました。
だって、話したら話したように伝わってしまう。でもその伝わったものは、私の抱えている気持ちの1%にも満たないくらいのものでしかなくて、そんなものを「わかる」とか「そう思ってるんだね」と理解されたら、言葉を発すれば発するだけ誤解されていくようなものではないかと思ってしまっていたのです。
当時、こんなふうにちゃんと言葉に整理できないままに、なんとなく口を噤んでいたのだけれど、今書きながら「ああ、だから話そうと思えなかったんだ」と納得しました。
大切な人や身近な人と死別した後、「なんでも言ってね」「つらかったら話聞くよ」と声をかけられることがあると思います。
でも、こんなことまで言ったら心配かけてしまうのではないかと躊躇することがあるかもしれないし、また、話さないからといって大丈夫なわけではないですよね。
井手代表は、「その現場で求められるのは、ただそばに居てくれる人。同行してくれる人」と話されていました。
話してもいい
話さなくてもいい
その沈黙の中にたくさんの想いがあることを感じながら、共に過ごす。
そんな存在になれたらと、グリーフ専門士/ペットロス専門士は学びを深めています。
トークショーに足を運ばれたのは、アート関係(興味がある)方とグリーフケア関係(興味がある)の方、半々くらいだと聞いています。
このトークショーは、アートだ、グリーフケアだという垣根自体を取っ払おうという試みだったように感じました。
そこには、もしかしたらケアをする側、される側という概念に対してのアンチテーゼも含まれていたかもしれません。
私自身ケアする側になることもあれば、ケアされる側になることもあります。
そのどちらもが私にとって必要な時間で、繰り返すことが自然であり、大切なリズムになっています。
そしてこれを書いている今も、専門士としての私と、グリーフを抱えた一人の人間としての私を行ったり来たりしながら過ごしていて、その狭間は時に、あわく交じり合うような感覚があります。
堀内さんは「自分が与えるだけでなく、受け取りながら」ということをおっしゃっていて、ケアがけして一方的な行為でないということを伝えてくださっていたように感じました。
死別に限らず喪失は人生の中に様々あり、誰もがグリーフ(喪失による悲嘆)を抱える当事者になる可能性がありますね。
このブログが、今、哀しみの中にいる方、そして、そうでない方にも、何かしら感じていただけるものになっていたら幸いです。
編集後記
今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。
人生の中に様々なグリーフがあるように、グリーフケアの形も多様であっていい。
私にとってはこうして文字にすることもまた、自身の大切なグリーフケアの一つです。
〇オンラインによるわかちあいの会(無料)・個人カウンセリングの日程確認とお申し込みは「グリーフサポートIERUBA」へ。
〇「哀しみに寄り添うグリーフケア基礎講座」
大切な人や身近な人と死別され、哀しみの渦中にいらっしゃる方にもご参加いただける講座となります。
死別後の暗闇の中、知識が今を生きる支えとなりますように。
〇「グリーフケア入門講座」「ペットロスケア入門講座」
こちらの講座は無料で開講しています。
支援者を目指す方、グリーフケアってなんだろうという方はこちらをどうぞ。
私もここから学び始めました。